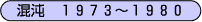

| 仲里 |
「あーまん」(※12)ができるのが何年でした? |

写真ひろば「あーまん」での一コマ |
|

大城弘明個展(あーまん) |
| (※12)「あーまん」;写真広場「あーまん」として、1976(昭和51)年、那覇市西消防署裏に開設、8月に第1回合同写真展開催。
|
| 大城 |
74年に東松さんなんかのワークショップ(※13)があるんですよ。その後ですから76年ですね。東松さんは沖縄に1年間くらい移り住んで、彼(比嘉)と付き合って。僕は、そんなに頻繁には会ってないですよ。ワークショップで5日間、一緒に鍛えられたというか。 |
| (※13)ワークショップ;1974(昭和49)年、写真学校WORK SHOP開校(八汐荘)。講師は東松照明・森山大道・荒木経惟ら。 |
| 仲里 |
「あーまん」ができるまでのいきさつを聞く前にちょっと。沖縄は72年に日本に復帰する。その復帰は、写真に限らず沖縄で何かを表現している人たちにとっては、大きな転機というか、変わり目だったような気がするんですけど、そのへんはどう思われますか。 |
| 大城 |
僕は卒業して、すぐ自称、フリーのカメラマンということで、1年間は東京で仕事をして、沖縄は撮っていないのですが、卒業の前の71年後半から、卒業して東京に行く72年の5月までは、結構、精力的に撮ってましたね。自分の生まれた村を。そのころは『生まれ島』というタイトルで、比嘉康雄さんとまったく同じタイトルで。
卒展のタイトルも『生まれ島』だったんですよ。最近はタイトルを変えて『地図にない村』というふうなテーマにして。やっぱり毎日、毎日がデモばっかりの写真で、考えてしまって。自分の足下を見つめ直そうと。それも沖縄戦の終焉の地で、一番の激戦地でしたから、いろんな戦争の痕跡が残っているわけですね。小学校4年くらいの時に、簡易水道の工事があって、村中、水道管敷設のために掘り起こした時に、何百体もの遺骨がでてきたんですよ。大人と一緒に一カ所に集めたのを覚えていて。あと、不発弾で、結構、遊んで。スクラップブームのころは集めたり。そういう風景が学生のころに写真に向かわせたと。それがずっと写真に関わった理由かも。 |
| 比嘉 |
僕は、復帰前も沖縄の現状を撮っていて、復帰に対していろんな…独立とか、なんやかんだがあって。それで、復帰に向かって、じゃあ、われわれ写真クラブはどうしようかという話があってですね…「毎日行動隊」というのがあったんです。写真クラブも何名か出て、結構、参加していて…復帰した途端、写真を含めて、元気がなくなってしまった。僕は、沖縄の日常を撮ろうということで、朝から晩まで車に乗って、あっちこっち回って風景を撮りまくった。それが72年11月の展示会で、それを東松さんが見て取りあげてくれた(※14)。 |
| (※14)東松さんが見てとりあげてくれた;1972(昭和47)年、『アサヒカメラ』連載「東松照明・沖縄通信」で、水島源晃・胡屋永幸・平良孝七・比嘉豊光が紹介される。沖縄通信は、後に『朱もどろの華』として本になる。 |
| 仲里 |
二人とも沖縄の状況的な位置から生活や風景といった日常性に視点を向けていくわけですが、「あーまん」をつくったいきさつについて聞かせてください。なにをめざそうとしたのですか。 |
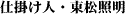
| 大城 |
先に東京の方でできていたんですよ。自主ギャラリーが。それでというか、東松さんのアジに乗せられたというか、みんなやる気になって。平良孝七さんも最初は。それに玉城惇博さん、奥平一夫、宮良信夫、嘉納(辰彦)、山城(博明)、(比嘉)豊光、僕も最初の設立のころは。
とにかくも玉城さんの事務所がミニギャラリーで、そこで毎週、誰かが写真展をやるということで、1年か2年続いたのかな。テーマはそれぞれ個人にまかせられていて、自分のなにを見せたいのか、なにを撮っているんだという、主張する場所としてあった。 |
| 比嘉 |
「あーまん」の前に、東松さんがもう一つ仕掛けたのがあるんですよ。「沖縄写真史を考える会」なんです。沖縄の写真史を洗い直そうということで。東松さんは「日本写真史」をつくったよね。あれの延長で、沖縄版をつくろうということで東松さんと平良孝七さんが中心になって、僕や映像をやっていた森口(豁)さん、それに大宜味の人。4、5回集まった覚えはあるが、東松さんが宮古へ行って、平良さんも動かなくなって、結局、続かなかった。 |
| 比嘉 |
それが極端に言えば、(石川)真生(※15)なんかが作った写真史になっているんですよ。 |
(※15)(石川)真生;大宜味村生まれ。1973年、WORKSHOP写真学校入学。『熱き日々inキャンプハンセン!!』『港町エレジー』『仲田幸子一行物語』『これが沖縄の米軍だ』など刊行
(※16)『大琉球写真帖』;1990(平成2)年7月、発行。第11回沖縄タイムス出版文化賞(特別賞)受賞。 |
| 比嘉 |
だから東松さんは、いろいろ仕掛けているんですよ。「あーまん」のときも東松さんが東京にもある自主ギャラリーを沖縄でもつくろうと。たまたま、玉城(惇博)さんが森山大道と友達で、森山大道は東京で「キャンプ」というグループを持っているもんだから、東松さんのグループと森山さんのグループが一緒になろうということで、「あーまん」ができたわけですよ。 |
| 仲里 |
山田さんは、ワークショップや「あーまん」などのグループ活動、それに東松さんの動きなどをどう見ていたんですか。 |
| 山田 |
先ほどから東松さんの話が出ているんですが、東松さんは、単なる仕掛け人ではないですよね。沖縄の写真界に、思想性を持たせたのは東松さんの影響が大きいと思うんですよ。東松さん自身が口に出して、そんなこと言わないけれども。
東松さんの写真を見ることによって、われわれは、写真というのはこういうものでなければいけないという、一つの方向性が示されたというふうに思うんですよ。東松さんの精神の底にあるのも、反骨精神だと思う。決して時代に甘えたり、呑まれたりしないで、いつでも何かを、批判精神を失わないでいきたいと。東松さんの写真の中には、それが脈々と生きている。「沖縄の中に基地があるのではなく基地の中に沖縄がある」ということだって、単なる基地の写真ではないですよね。明らかに東松照明という人の世界が描かれているわけです。それが知らず知らずのうちに「あーまん」の誕生であり、「ざこ」もそうだったんでしょうけれども、そういう写真活動を通じて東松さんの、東松精神が芽生えて、ずっといままで尾を引いているんだろうと思いますね。 |
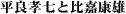
| 大城 |
そういえば写真協会(※17)の仕掛けの話もありましたよね。(平良)孝七(※18)さんか、(比嘉)康雄(※19)さんなんかで。 |
| 比嘉 |
仕掛け人は東松照明で、平良孝七と僕と3人。みんな逃げ出してよ。 |
| 大城 |
流れとしては、「あーまん」の活動があって、本土の自主ギャラリーのみなさん方との「ぬじゅん展」(※20)がダイナハであって、その後に沖縄写真協会を設立しようという動きがでて。 |
(※17)写真協会;沖縄県写真協会。沖縄県芸術祭写真部門を支援、発展させることを主目的として1981年(昭和56年)発足。会長・比嘉康雄。
(※18)(平良)孝七;平良孝七。1939(昭和14)年、大宜味村喜如嘉生まれ。1977年、写真集『パイヌカジ』で第2回木村伊兵衛賞受賞。1994年死去(55歳)。
(※19)(比嘉)康雄;比嘉康雄。1938(昭和13)年生まれ。1976年、『おんな・神・まつり』で第13回太陽賞受賞。2000年5月死去(61歳)。
(※20)「ぬじゅん展」;「ぬじゅんin沖縄・大和写真展」(ダイナハ/那覇市)。1979(昭和54)年3月開催。 |
| 比嘉 |
それも沖展に対する、もう一つの展示会をやろうということで、写真協会をつくろうとしたわけです。県展には写真部会がなかったので、協会をつくって県展をやろうということでした。とりあえず比嘉康雄さんが会長になって。 |
| 仲里 |
比嘉康雄さんと平良孝七さんは、どういうふうな存在でしたか。 |
| 山田 |
比嘉康雄さんも平良孝七さんも、(比嘉)豊光さんと同じように沖展に応募して入選、入賞していますよね。康雄さんはお巡りさんを辞めて、東京の写真学校に何年か行って、夏休みや春休みの度に帰って来ては撮っていましたね、それが『生まれ島・沖縄』(※21)という写真集です。
いままで沖縄の基地を本土のカメラマンが紹介していて、もう沖縄中が反米、反基地闘争に揺れているという印象ですよ、本土の方ではね。そうした写真しか東京に報道されていない。ところが比嘉康雄さんが『生まれ島・沖縄』という本をだす。これはもう、沖縄に生まれて、沖縄で育った人でないと撮れない写真ですよ。単に反米、反基地だけじゃ撮れない、われわれはここで生活しているんだ、ここで生きているんだという写真。僕は、そう思っているんです。 |
| (※21)『生まれ島・沖縄』;比嘉康雄、処女写真集。1972(昭和47)年4月刊行。 |
| 山田 |
孝七さんは最初、(琉球)新報にいたのかな。それから県の広報課に就職した。当時は復帰前ですよね。彼自身が革新の渦の中に飛び込んでいった。彼の撮る写真は、そういう闘争の写真であり、抵抗の写真だったですね。
|
| 大城 |
僕は平良孝七さんの方が先に知り合いですね。身近すぎて、兄貴分という感じがします。革新の広報マンと言われ、革新共闘会議の本なんか出してね。平良さんの写真が、ある意味で圧倒的におもしろくなったのは、県政が代わって、復帰後ですね。僕はそう思います。木村伊兵衛賞をもらった『パイヌカジ』、それから『カンカラ三線』。オバーの後ろ姿がいっぱいある写真集が好きでしたね。
比嘉康雄さんは、僕の琉大の卒業写真展を見に来ていて、そのときに初めて会いました。僕も「生まれ島」というタイトルで撮っていて、康雄さんも「生まれ島」というので本を出して、タイミングが結構、合っていたもんだから、非常に親近感を持てて。
比嘉さんがまつりを撮りはじめたころ、僕も結構、まつりを撮っていて、まつりの現場でしょちゅう会って、いろいろ教えてもらいましたね。僕なんかは、新聞社の仕事の場合は名刺一枚で、強引に撮らせてくれと押しかけて、撮ってはパッとハゲタカのごとく逃げて帰る。締め切りもあって。
でも比嘉さんは、事前調査に入って、あいさつ回りして、ちゃんと名前も覚えてもらって、顔も覚えてもらって。それからまつりの前の日に入って、準備風景からもう一度、調べながら、こつこつとやって積み重ねていく。いつも、いつも、頭が下がりましたね。 |
| 比嘉 |
孝七さんとは、僕は学生時代からの付き合いですね。71年に東松さんを連れてきたのが平良さんで、東松さん絡みで付き合っていました。県庁で働いていて、お金もあるから飲ませてもらたりして(笑)。比嘉康雄さんはですね、「あーまん」に引っぱったんですが、断ったんですよ。それほど付き合いがなくて…79年の「ぬじゅん展」のときには一緒にやりました。 |
| 仲里 |
平良孝七さんが木村伊兵衛賞をもらうよね。比嘉康雄さんは、その前年に太陽賞をもらう。さらに、その前には東松照明の『太陽の鉛筆』(※22)が出ている。このへんのところをどう見るかですが。 |
| (※22)『太陽の鉛筆』;1973(昭和48)年、7カ月間の宮古島滞在を経て『カメラ毎日』に「太陽の鉛筆 沖縄」として連載。1975年、写真集『太陽の鉛筆』刊行。 |
| 大城 |
孝七さんは、「似ている」と言われるのが一番、嫌いでしたね。 |
| 山田 |
どうしても影響、受けるんだよね。アングルも似てくるし、被写体も似てくるしね。 |
| 比嘉 |
平良さんの撮り方と東松さんの撮り方は、ぜんぜん違うと思いますよ。性格も違うし。平良さんは、結構たくさん撮っていて、東松さんよりも早い時期から撮った写真もあって…だけども選びきれなかった。というのは闘争を撮っていて、自分の作品を見つけきれなかった。東松照明さんが出てきて、たくさん賞をもらっていくなかで、自分にもたくさんあるのにということで、ワークショップに来ていた森山大道に見せて、自信をつけて、そして、出して賞をもらった。ただ、何年か、東松さんと平良さんは一緒にいるし、それに場所が場所だけに、カメラアングルだって似てくる。「似ている」と言われてもしようがないですよ。言えることは、東松さんほど写真がうまいというのは…もう本当に脱帽しますよ。 |
|

