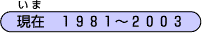

| 仲里 |
80年代に入ると、沖縄の写真も多様化していったといえるのではないでしょうか。東松照明さんも『太陽の鉛筆』から『光る風沖縄』になって、カラーに変わって、ついにモノクロには復帰しなかった。山田さんもカラーを撮りはじめているころですよね。 |
| 山田 |
本土復帰して、しばらくしてね、画家の安仁谷正義(*23)さんと私とで共同作品をつくれという指令がありまして。画家だから、どうしたって色付きじゃないといけないというんで、カラーをスライドでやってみたんです。現像、焼き付け、作品化してみたけど、色がぜんぜん出てない作品になってしまった。絵だと好きな色を塗っていけばいいんだろうけれども、写真の世界はフイルムから現像と、もろもろの制約を受けるし、特にカラーだとそうです。そんなカラーだと、やる気はない、とやめた時代があるんですよ。 |
| (※23)安仁谷正義;あだにやまさよし。1921(大正10)年生まれ。沖縄における戦後の美術の中心的存在として活躍。琉球大学美術工芸科教授。1967年死去(46歳)。 |
| 仲里 |
その後、また撮りはじめますね。いつごろになりますか。 |
| 山田 |
1980年以降でしょうね。過去のモノクロのリアリズム写真から一応、卒業という形になるわけですけれども。今度は色との闘いになっていくわけですよ。どうやったら本物の色が出せるかっていう。ただフイルムや現像に頼るのではなくて、ある程度、自分の技術で左右できるようになりますからね。本当に自分の満足できる色が出せるようになったのは、しばらくしてからですよ。本物の色が出せるようになって、自分の好みの被写体を選んでいくわけです。ずいぶんカラーには苦労しましたね。 |
| 仲里 |
被写体の選び方を含めて、写真そのものが変わったということですか。 |
| 山田 |
今まで、僕が撮ってきたリアリズムの写真の世界とはぜんぜん違う、180度の転換になりました。悪く言えば、写真を楽しむ世界に入っちゃったですね。創作というか、自分がカラーでないと出せない被写体を選ぶ。単なる被写体を再現するっていうことではなく、被写体を自分で創り直すという意気込みですよ。だから、カラーになってはじめて写真を創作したっていう自覚が持てるようになりました。 |
| 大城 |
80年代は(石川)真生と(比嘉)豊光ががんばりはじめたころでもあるんですよ。それに、比嘉康雄が一般に出てくるというか。 |
| 大城 |
真生ががんばっているね。3、4冊つくっているし。比嘉康雄さんの写真集も80年代が多いんじゃないかな。写真展は毎年、毎年の恒例の展示会ばかりという感じですね。名護の「フォトシンポジウム」が87年から隔年にあって、92年には沖縄の復帰20周年の割と大きな展示会(※24)があって。 |
| (※24)割と大きな展示会;復帰20周年記念事業「写真で考える沖縄戦後史展」が那覇市民ギャラリー、リウボウ特設会場などで開催。 |
| 仲里 |
80年代、90年代は近過去のせいなのか、うまく対象化できないところもある。 |
| 大城 |
95年になると、また元気が出るんですよ。95年に東松さんの写真展と、戦後50年展と連動して連続写真展、その後に「映像と話の会」やって、さらにその後に12人の眼展の「カジマーイ」をやってね。 |

「写真ひろば・あーまん 連続写真展−戦後50年沖縄」 |
|

「東松照明写真展 沖縄マンダラ」 |
|

「琉球烈像−写真で見るオキナワ」写真展 |
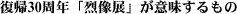
| 仲里 |
(比嘉)豊光さんから見て、80年代、90年代の沖縄の写真シーンはどのように見えますか。 |
| 比嘉 |
僕個人の流れでしか言えないんだけれども…沖縄写真協会をつくって、県展をやる形で、仕掛けていくわけだが、それが結局、若いのがついてこれなかったということです。それに、いろいろやってはいるけれども、ある意味で体制側とつるんだ展示会であったり、あるいはヤマトゥが金を出してのことだったり、ほとんどがコンテスト形式であったりした。そういう形の写真だから、要するに時代とか、風土とか、そこらへんを記録しながら沖縄を撮るということができなかった。だから80年代は動きが無かったんじゃないかと… |
| 仲里 |
80年代から90年代にかけて写真家個別には、いろいろテーマを持って活動はしていただろうけれども、60年代後半から70年代にかけてのような、ある求心力を持って、一つの場をつくりあげていくということがなかった。テーマも方法も拡散していく中で、それぞれの写真家が、それぞれの流儀でやっていた時代だったといえるのではないだろうか。まあー、「あーまん」のメンバーが時々、思い出したように連続展をやったにしても、それ以降の沖縄の若手の世代がなかなか、見えてこないというのがある。そのへんはどう思いますか。 |
| 大城 |
ここ2、3年、若い人たちが増えてきたと思いますね。この間の「烈像展」(※25)にも、結構、若い人たちがたくさん参加してくれたし。これから僕らとはまったく違う写真というか、新しい分野の写真がどんどん出てきているんで、この間みたいに、まとまって何かをやるということができれば、新しい流れになるかもしれませんし。 |
| (※25)「烈像展」;2002(平成14)年7月、那覇市民ギャラリー、前島アートセンターで開かれた「フォトネシア/光の記憶・時の果実ー琉球烈像展」。 |
| 比嘉 |
世紀の変わり目であったわけで、何かあるという感じはするんだけれども、要するに沖縄とか、時代とかをほんとうに見ようというか、そこらへんが僕には、実をいうと見えてこないわけよね。若い人が、写真集をつくってみるとか、個展をやってみるかというような、そういう表現をしているかどうかが、まだ見えてこないのがちょっと。 |
| 仲里 |
そうだね。われわれの世代というのは、カメラを持つということが、何か世界とわたりあうというような構えがあったよね。80年代、90年代になって非常に手軽なコンパクトなカメラが流行って、一億総カメラマンいわれるくらいに写真が日常にあふれ、最近ではデジタルが主流になりつつある。写真状況が大きく変わりつつある。ベンヤミンの『複製技術時代の芸術』は、もういっぺん書き直されなければならない時代にきているという気もする。 |
| 仲里 |
昨年、われわれがやった「烈像展」の意味は、二つあると思うんだよね。一つは沖縄から仕掛けていったということ。二つ目は若手の写真家との交流が実現したということ。若い人たちが市民ギャラリーに足を運び、そこに自分たちとは違う写真を発見しなおしていく現象が起こった。逆に写真のミドル世代も前島のアートセンターで新しい動きに触れる。「烈像展」の異なる二つの場は、そういうふうな空間ではなかったのか、と僕は思ったりするわけ。そこでやったことが、山田さんの写真展につながているし、何か生まれてきそうな気がしますね。 |
|


