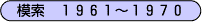
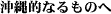
| 仲里 |
山田さんが審査員になられて、審査員の立場から見て沖縄の写真は変わったのでしょうか? 変わっていったとしたら、どういう方向で変わっていったのでしょうか。 |
| 山田 |
内地だとか、海外の旅行の写真だとか、記念写真的な作品が増えたりするわけです。それで、沖展の運営委員長だった豊平(良顕)さんが、一種のゲキを飛ばされたんですね。取材をもっと沖縄に、自分たちのふるさとの沖縄に、目を向けろという主張があって、写真部の運営委員が応募者にその説を広めたわけなんです。その豊平さんの、何というかなあ、クレームがついたおかげで、次の年度からいい作品が集まるようになったんですよ。とにかく、沖縄を取材して作品を作れということになった。シーサーだとか、石畳とか、沖縄の風景が主になって出てくるわけですよね。それが何年か続いた。まあ、僕らとしては、前よりははるかに充実した内容だと思ったんだけれども。 |
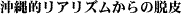
| 山田 |
今度は、逆に本土の写真家がクレームをつけるわけですよ。なぜ、沖縄の写真愛好家は沖縄だけに目を向けるんだと。もっと、もっと、ほかのところに目を向けないといけないという。本土のプロの写真家の忠告があってね。 |
| 大城 |
 60年代後半から70年代はじめにかけて、本土から有名な写真家がたくさん、写真教室にきてるんですよ。僕も知らないころなんですけど、東松照明さんですね。写真連盟(※5)の写真教室の講師もしているんですよ。ほとんど同じ時期に、アサヒカメラの創刊20周年(※6)でね。木村伊平衛(※7)さんとか、稲村隆正さん、中村正也さん、奈良原一高さんとかもきているし。その翌年もそうそうたるメンバー(※8)ですよね。三木淳、細江英公、佐藤明、篠山紀信、横須賀功光、それに秋山庄太郎、林忠彦などという感じで。あの前後は、影響を受けたのではないですか。 60年代後半から70年代はじめにかけて、本土から有名な写真家がたくさん、写真教室にきてるんですよ。僕も知らないころなんですけど、東松照明さんですね。写真連盟(※5)の写真教室の講師もしているんですよ。ほとんど同じ時期に、アサヒカメラの創刊20周年(※6)でね。木村伊平衛(※7)さんとか、稲村隆正さん、中村正也さん、奈良原一高さんとかもきているし。その翌年もそうそうたるメンバー(※8)ですよね。三木淳、細江英公、佐藤明、篠山紀信、横須賀功光、それに秋山庄太郎、林忠彦などという感じで。あの前後は、影響を受けたのではないですか。 |
(※5)写真連盟;1966(昭和41)年、水島源晃・山田實・親泊康哲らが発起人となり設立。会長、水島源晃。
(※6)アサヒカメラの創刊20周年;1969(昭和44)年、沖縄大撮影会が首里周辺と中城公園で開催。講師は木村伊兵衛、稲村隆正、中村正也、奈良原一高。
(※7)木村伊平衛;写真教室を沖縄タイムスホールで開催。1965(昭和40)年。
(※8)そうそうたるメンバー;1970(昭和45)年のニッコールクラブ沖縄撮影会(中城公園)に、三木淳・細江英公・佐藤明・篠山紀信・横須賀功光らが講師として来沖。 |
| 山田 |
大城さんが言った先生方の前に、関西の岩宮武二(※9)という先生がきた。この人は大阪芸大の先生で、指導が上手でした。話しも上手で、ずいぶんアマチュアの写真愛好家が集まって、写真教室も開いたり、勉強になりましたよ。岩宮さんは、沖縄的なものからの脱皮を言うわけですよ。
その前には濱谷浩(*10)さんがきて、写真教室をやった。濱谷さんは、とにかく、沖縄のみなさん、これからどんどん変わっていくから、ぜひ、記録を撮りなさいよ、と。そういう話は、濱谷さんが最初でしたね。そのような本土の写真家の指導や忠告などがあって、この辺から混沌としてくるわけです。ちょうど、そのころに、基地に対するデモや、反米基地闘争がはじまって、それこそ写真界も激動の時代を迎えていくことになる。 |
(※9)岩宮武二;1966(昭和41)年、岩宮武二写真教室が首里博物館で開催。岩宮氏は「沖縄的リアリズム、即ち石垣や赤瓦の屋根などローカルなものが画面を占める作品、これは長い間、沖縄の写真界をささえてきた必要な素材には違いないが、同時にこれから新しい写真の境地をめざして脱皮するための障害ともなっている」と指摘。
(※10)濱谷浩;1962(昭和37)年、先島取材に来沖。琉球新報写真教室講師に招かれる。 |
|
 60年代後半から70年代はじめにかけて、本土から有名な写真家がたくさん、写真教室にきてるんですよ。僕も知らないころなんですけど、東松照明さんですね。写真連盟(※5)の写真教室の講師もしているんですよ。ほとんど同じ時期に、アサヒカメラの創刊20周年(※6)でね。木村伊平衛(※7)さんとか、稲村隆正さん、中村正也さん、奈良原一高さんとかもきているし。その翌年もそうそうたるメンバー(※8)ですよね。三木淳、細江英公、佐藤明、篠山紀信、横須賀功光、それに秋山庄太郎、林忠彦などという感じで。あの前後は、影響を受けたのではないですか。
60年代後半から70年代はじめにかけて、本土から有名な写真家がたくさん、写真教室にきてるんですよ。僕も知らないころなんですけど、東松照明さんですね。写真連盟(※5)の写真教室の講師もしているんですよ。ほとんど同じ時期に、アサヒカメラの創刊20周年(※6)でね。木村伊平衛(※7)さんとか、稲村隆正さん、中村正也さん、奈良原一高さんとかもきているし。その翌年もそうそうたるメンバー(※8)ですよね。三木淳、細江英公、佐藤明、篠山紀信、横須賀功光、それに秋山庄太郎、林忠彦などという感じで。あの前後は、影響を受けたのではないですか。