女踊りのルーツは、衣裳やその優美な手の振りなどから神事を司どる祝女(ノロ)であるといわれる。そのためか舞台芸能として完成し上演されたのは若衆踊りなどよりはるかに遅く、18世紀に入ってからである。組踊の創始者玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)によって、江戸の薩摩屋敷で「綛掛」系統の「くりまへ踊り」が踊られたのが記録されている。
後に代表的な女七踊りが完成され、女踊りは文字通り琉球舞踊の華として、それぞれの時代の舞踊家たちによって洗練され、今日に踊り継がれている。
|
|
||
女踊りのルーツは、衣裳やその優美な手の振りなどから神事を司どる祝女(ノロ)であるといわれる。そのためか舞台芸能として完成し上演されたのは若衆踊りなどよりはるかに遅く、18世紀に入ってからである。組踊の創始者玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)によって、江戸の薩摩屋敷で「綛掛」系統の「くりまへ踊り」が踊られたのが記録されている。 |
| ※画像をクリックすると拡大画象やビデオが表示されます。 | |||
 |
 |
 |
 |
| 本貫花 (ムトゥヌチバナ) |
天川 (アマカー) |
綛掛 (カシカキ) |
柳 (ヤナジ) |
 |
 |
 |
 |
| 作田節 (ツィクテンブシ) |
伊野波節 (ヌファブシ) |
諸屯 (シュドゥン) |
稲まづん (ンニマジン) |
 |
 |
 |
 |
| 四つ竹 (ヨツダケ) |
苧引き (ウービチ) |
瓦屋節 (カラヤーブシ) |
本嘉手久 (モトゥカディク) |
 |
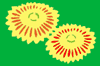 |
||
| 女こてい節 (イナグクティブシ) |
|||
| [ もどる ] |
|
写真:砂川敏彦 |