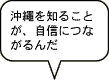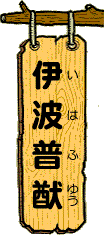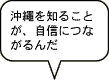
 |
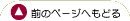 |
1910(明治43)年に沖縄県立図書館ができた時、普猷が集めた資料(しりょう)は4000点をこすほどになっていた。図書館の館長をつとめるようになったかれは、研究をつづけながら、沖縄の歴史や文化を人々に知らせる活動をはじめた。これを心よく思わない人たちから、いろいろないやがらせを受けたものの、それに負けることなく研究をつづけたかれは、図書館長をやめると東京にうつり、沖繩の研究にいっそう打ちこんだ。
伊波普猷がおこなった研究の中で、きちょうな資料となったのがオモロだった。オモロは神や王様、英雄(えいゆう)、戦い、そして自然などをうたったもので、大昔の人々のくらしや考え方がよくわかるものだった。
それまでわずかな人にしか知られていなかったオモロを研究しながら、かれはその成果を本や新聞に発表した。これにより、自信をなくしていた沖縄の人たちも、沖縄のすばらしさを見直し、ほこりを持つようになったといえる。

伊波普猷の墓(いはふゆうのはか) |
沖縄の研究に一生をささげた伊波普猷は、最後の本『沖縄歴史物語』を書き終えたつぎの年に72さいでなくなった。かれが残した300をこえる論文や本は、沖縄県立図書館で今も広く使われている。 |
|
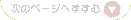 |
|
|
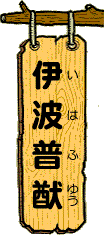
 |