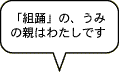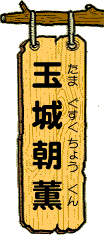|
25さいの時、徳川家宣(とくがわいえのぶ)が6代目の将軍になったことのお祝いをのべるため、朝薫は、美里王子(みさとおうじ)といっしょに江戸へ行った。それから、王様の命令でたびたび日本(ヤマト)へ行くようになった朝薫は、人形しばいや狂言(きょうげん)を見るようになり、日本文化を深く知るようになった。
そのころ琉球は、中国との行き来をさかんにおこなっていた。その中には、中国から400人以上の使者がおとずれる琉球王国の大切な行事(中国の皇帝が琉球の新しい王様をみとめるためのぎ式)もふくまれていた。朝薫が32さいの時にも、中国からの使者がたくさんくることになり、那覇港を大きくつくり直す工事がおこなわれた。朝薫は、役人のひとりとしてこの工事の指どうをまかせられ、つづいて、使者をもてなすために音楽やおどりを指どうする役割もまかせられた。

護佐丸の墓(ごさまるのはか) |
江戸で見た能(のう)や狂言をいかして、「琉球の音楽やおどり、そして言葉を使った劇(げき)をやりたい」と思っていた朝薫は、琉球の昔話をテーマにした出しものを考えはじめた。こうして、護佐丸(ごさまる)と阿麻和利(あまわり)の話をもとに『二童敵討(にどうてきうち)』という台本を書き、つづいて『執心鐘入(しゅうしんかねいり)』を書きあげた。
|