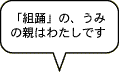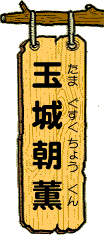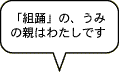
 |
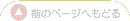 |
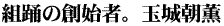
 玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)は、おさないころから音楽の才能をあらわし、組踊(くみおどり)という、沖縄の古い音楽とおどりを取り入れた劇(げき)を考え出した人である。 玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)は、おさないころから音楽の才能をあらわし、組踊(くみおどり)という、沖縄の古い音楽とおどりを取り入れた劇(げき)を考え出した人である。
玉城朝薫は、1684年、首里儀保(しゅりぎぼ)のゆたかな家がらに生まれたが、おさないころ父と母をなくしたため、おじいさんに育てられた。しかし、そのおじいさんもなくなったため、わずか9さいの朝薫が、おじいさんのあとをついで玉城間切(たまぐすくまぎり)の主になった。
それから13さいになった朝薫は、首里城(しゅりじょう)につとめることになった。しかし、このころの首里城では、たとえ士族でも、おどりや楽器がひけないと役人になることはできなかったため、朝薫は楽器やおどりのけいこにはげみながら、日本語の勉強にも力を入れた。
まじめな働きぶりがみとめられ、21さいの時、越来王子(ごえくおうじ)のおともとして、朝薫は薩摩(さつま)にわたった。ここで朝薫は、能(のう)の好きな藩主(はんしゅ)・島津吉貴(しまづよしたか)を前に、『軒端の梅(のきばたのうめ)』をおどってみせ、すばらしい才能をひろうした。 |
|
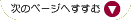 |
|
|
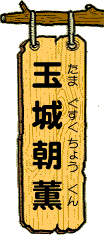
 |