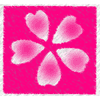八重山の島々には宝石のような輝きを放つ古謡や節歌が無数に存在する。自然や労働のなかで生まれた結晶のようなものだろう。生産と祭りと生活がひとつとなり、共同体との一体感をみなぎらせる巻踊り(ガーリ)などもその様なものだといえる。これらをバックボーンに首里から八重山へ渡った比屋根安弼(ひやねあんそく)によりもたらされた「伝書」をもとに、八重山古典民謡に振り付けられたのが、勤王流八重山舞踊の始まりだという。首里城で宮廷舞踊として磨かれた舞踊と違い、祭祀舞踊に感じる無垢な清々しさを八重山舞踊に強く感じる。そして、今日においても威厳に満ちた創作舞踊が創られ続けているのは驚くばかりである。