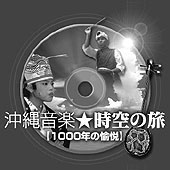 17世紀から18世紀に、本土から伝来した芸能。“京太郎”は京都からきた太郎という意味である。人形を使い家々の門で芸を披露した。法事があるときは“念仏歌”を歌った。この京太郎の伝来により、口説(五七五調の句を繰り返す歌謡)の流行、念仏系歌謡であるエイサーの誕生をうながすことになった。また、京太郎は組踊り、サンシン歌、歌劇などに大きな影響をもたらした。この京太郎の伝来は沖縄音楽に異変を生じさせる事件であったことに間違いないものである。現在、京太郎芸は、沖縄市の泡瀬(県指定無形文化財)と宜野座村宜野座に伝承されている。
17世紀から18世紀に、本土から伝来した芸能。“京太郎”は京都からきた太郎という意味である。人形を使い家々の門で芸を披露した。法事があるときは“念仏歌”を歌った。この京太郎の伝来により、口説(五七五調の句を繰り返す歌謡)の流行、念仏系歌謡であるエイサーの誕生をうながすことになった。また、京太郎は組踊り、サンシン歌、歌劇などに大きな影響をもたらした。この京太郎の伝来は沖縄音楽に異変を生じさせる事件であったことに間違いないものである。現在、京太郎芸は、沖縄市の泡瀬(県指定無形文化財)と宜野座村宜野座に伝承されている。