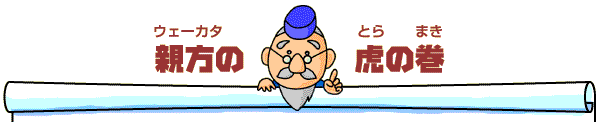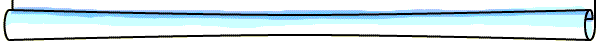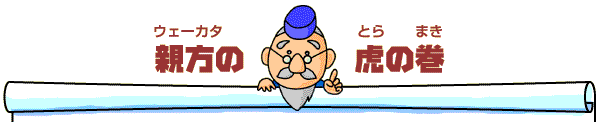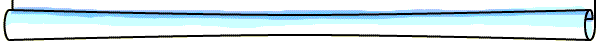|
●江戸上り(えどのぼり)
 |
| 江戸上りのさいに演じられた舞楽(ぶがく)の図(部分)。沖縄県立博物館蔵。 |
1609年,薩摩(さつま)に敗れた琉球は,江戸幕府の制度のもとに組み込まれました。
それにより島津氏にしたがわされることになった琉球は,国王の代替わりごとに,その就任を感謝する使節・謝恩使(しゃおんし)を,将軍の代替わりごとに,これを祝う使節・慶賀使(けいがし)を幕府に送ることになりました。これが“江戸上り”で,1644年から1850年の間に18回おこなわれました。
“江戸上り”の一行は「異国風=中国風」をよそおわされ,島津氏にともなわれて行くのがならわしでした。
一行は100人程度で,正使(王子)・副使(親方)をはじめ,多くの役人や楽童子(がくどうじ)などで構成されていました。往復およそ300日の旅の間,日本文化とのふれあいや,学者・芸能家などとの交流もあり,“江戸上り”はそれ以後の琉球文化に,大きな影響をあたえました。
|