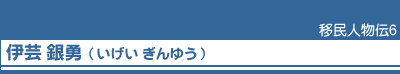|
 移民地で生き抜くためには日系人への偏見や戦争での排日運動の壁につきあたりながら、いろいろな職業に就かなければなりませんでした。伊芸銀勇の人生は、数々の職業をわたりあるいた一移民の波乱万丈の歴史といえます。そこには、不屈の魂をもった移民の誇りとたくましさが感じられます。 移民地で生き抜くためには日系人への偏見や戦争での排日運動の壁につきあたりながら、いろいろな職業に就かなければなりませんでした。伊芸銀勇の人生は、数々の職業をわたりあるいた一移民の波乱万丈の歴史といえます。そこには、不屈の魂をもった移民の誇りとたくましさが感じられます。
銀勇は1908年(明治41)、當山久三と同郷の金武村字漢那に生まれました。小さいころから移民の話をよく耳にする環境に育ったのです。周囲には海外に移民していた親戚や知人もことのほか多かったのです。6人兄妹の長男で母親が病気がちであったことで、勉強どころではなく懸命に農家の手伝いをせざるを得ませんでした。しかし、1929年(昭和4)には沖縄師範学校を卒業し金武小学校で教鞭(きょうべん)をとるまでになりました。
銀勇がペルーに渡ったきっかけは、日本人会幹部から誘われた小学校教師の仕事でした。1934年(昭和9)のことです。学校での月給は130ソーレス(日本円で100円)で昇給は毎年10円というものでした。これは当時「ソテツ地獄」で知られた沖縄県の教職状況を考えると、夢のような話でした。
1937年(昭和12)銀勇はリマ市近郊にあった南光学園(日本語学校)の校長になりました。しかし、そのころ妻がマラリアにかかり他界するという思わぬ試練にあいました。銀勇は涙をこらえて五か月にしかならない子どももかかえて再出発を誓ったのです。
1941年(昭和16)になると国際情勢の悪化にともない、日本教育は禁止されました。銀勇は南光学園を辞め、長年の夢だった農場経営に乗りだします。借金で土地を借りバナナ園を始めたのです。ところが戦争が始まると、銀勇は北米追放の命令を下されました。さいわい借地地主の取り計らいで、ペルーに残ることができたのです。それからは日系人は敵国人として扱われ、財産の没収や借地からも追い出されました。その後、ペルー人との共同でピアノ修理と販売の事業、戦時中での日本語教室、農業経営と働きつづけたのです。
ようやく戦争も終わり、銀勇は伊芸学園という日本語とスペイン語の学校を始めました。この事業も家主が学校のライセンスのないのを密告したことで閉鎖されました。その後、雑貨店を経営しながら農業もつづけました。そのころから、銀勇も経済的に安定をみせ、移民の成功者と言われるようになりました。
銀勇は1968年(昭和43)のペルー沖縄県人会会長の就任を始め、さまざまな要職を勤めました。1974年(昭和49)には、ペルー中央日本人会会長にも就任しました。また、1978年(昭和53)に勲五等双光旭日章(しょうこうきょくじゅつしょう)を受章しました。
|